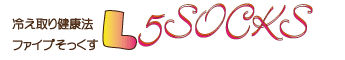ファイブそっくす/冷え取り通信 1
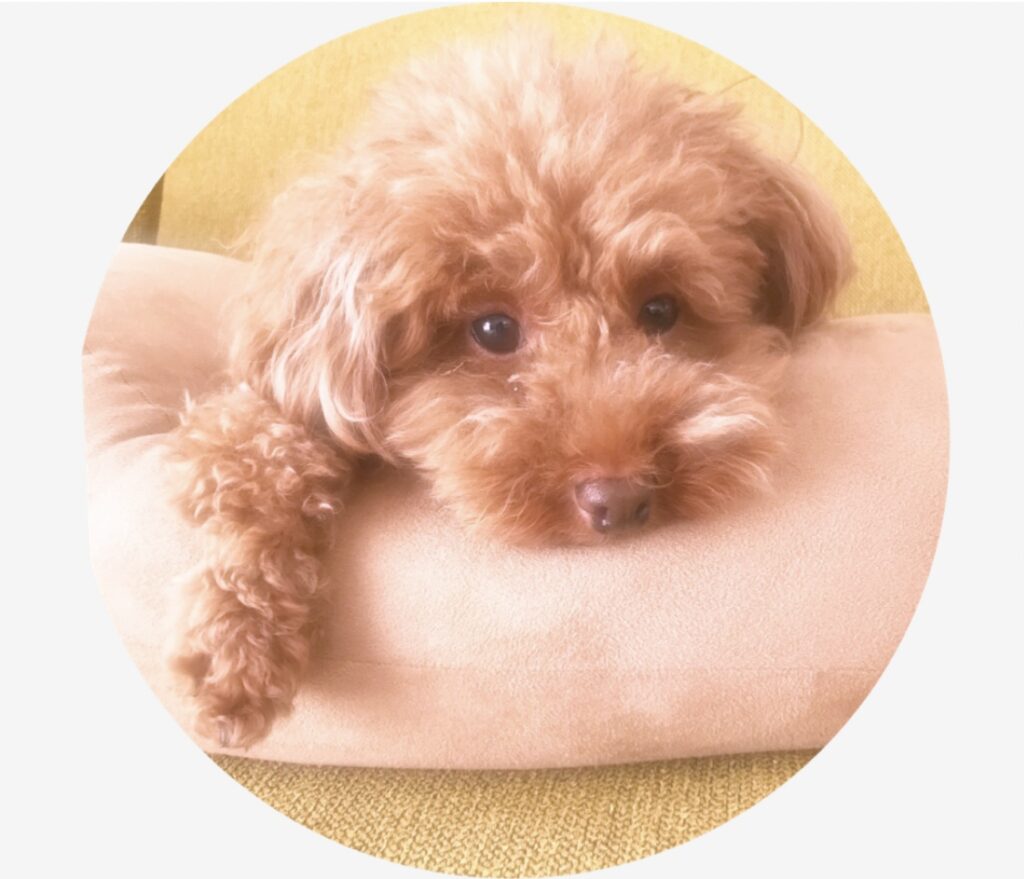
ファイブそっくす
冷え取り通信1
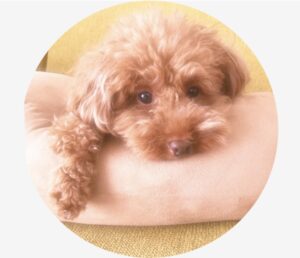
冷え取り通信
冷えの原因と対策
2003年 9月号
冷えの原因と対策(頭寒足熱)
血液の働きについて
血液は全身の様々な組織に循環して酸素や二酸化炭素、栄養素、ホルモン、代謝から生み出される生産物や老廃物の運搬、ウイルスなどからの感染抑制や免疫、けがをした際の止血、体温調節、など生命維持に必須な役割を果たしています。
血液が常に滞りなくサラサラと流れ続けていることが健康のためには最も大切なことです。血流の悪い状態を「冷えている」状態と東洋医学では定義しています。
「冷え」で血管が縮むと血行が悪くなり、いわゆる「未病」(病気ではないが健康な状態から離れつつある状態)になります。血行が悪くなると内臓の働きが低下してしまい、そのままにしておくと疲れやすく「なんだか調子が悪い」「睡眠の質が気になる」など身体が何らかのサインを出しはじめます。
冷えの原因は?
1、もともとある「冷え」
人は2足歩行になり、脳や内臓に多量の血液を使うために誰もが「体温は上半身が高く」「下半身は低く」なっています。そして末端の足元はより一層冷えています。
身体の上半身と下半身の温度差が激しいと血液の流れに大きな影響を与えて、さまざまな不調の原因になってきます。 足もとが「冷たい!」と感じるのは正常な感覚です。
しかし冷えが強すぎると反対に「ほてり」として感じるようになってしまいます。これは要注意です。
2、食べ過ぎによる「冷え」
食事の時は消化に多量の血液を使います。特に消化に力を要する物すなわち「自分より大きい動物性の肉」を食べると血液は消化をする臓器に集中し、身体全体からみると「冷える」状態になります。冷えとりの観点ではそれに加え動物性の食品や甘いものや果物、生野菜、食品添加物の多く入ったものなどは、身体を冷やすと考えます。 食べ物の性質からも考える事が大切です。
どんな食物でも「よく噛むことで消化しやすい状態」にして“食べ過ぎをしない”ようにすることが重要です。どんなによい食べ物であっても、身体にとって必要以上の量は負担(毒素)になってしまいます。
デトックス出来なかった老廃物などが内臓や血管などに血管プラークという形での壁に溜まり血管が細くなり、その結果血液の循環が悪くなります。「冷え」で血管が縮み硬化したと同じ状態になります。
また「冷えとり」をされている方から「身体を冷やす食べ物をたくさん食べてしまった。」とご相談をいただくことがよくあります。「食べてしまった」という考え方で後悔するのではなく感謝して戴くことが大切です。
気持ち次第で身体の冷え方も変わってくると思います。
3 、感情の 乱れによる「冷え」
様々な出来事で感情が乱れると自己中心的な考え方になってしまったり、自分本位な行動をしてしまう場合があります。イライラしたり、クヨクヨしたり、カリカリしたりする人も多いです。生きていると様々な出来事が起こります。感情の乱れで血液の巡りが悪くなり、身体を冷やす原因になります。
そんなときは少し足元を温めてみてください。少し深呼吸してみてください。半身浴をしてみてください。1枚靴下を増やしてみてください。焦りがちですが少しずつ気持ちがほぐれていきます。
頭寒足熱とは
足もとを温かくし、上半身は涼しくすると身体全体の血行が良くなり、内臓の働きも活発になっていきます。
東洋医学の「気血水論」を基にしており、全身にエネルギーをスムーズに循環させることが出来ると考えています。
頭寒足熱が基本の冷えとり健康法になります。半身浴は中でも理想の頭寒足熱の状態を作ります。半身浴の足元の温かさを維持するために靴下の重ね履きをして上半身をなるべく薄着にすること。寝ている時にも足元に湯たんぽを入れて頭を冷やすことで頭寒足熱の状態を保ちます。
血管をホースに例えると「冷えている」状態の時はホースを潰しているようになり血液を心臓から送るときにたくさんのエネルギーが必要になります。圧力をかけて血液を送るということになります。(血圧の高い状態)温めることでホースの圧力が穏やかになり身体は血流の良い状態になります。身体的にも精神的にも調子の良い状態になっていきます。
様々な原因で血流が悪い状態になってしまいますが、原因を一つずつ探りながら生活や考え方を見つめ見直していく生き方をファイブそっくすは提案します。
©「冷え取りの手引き」2023 ファイブそっくす